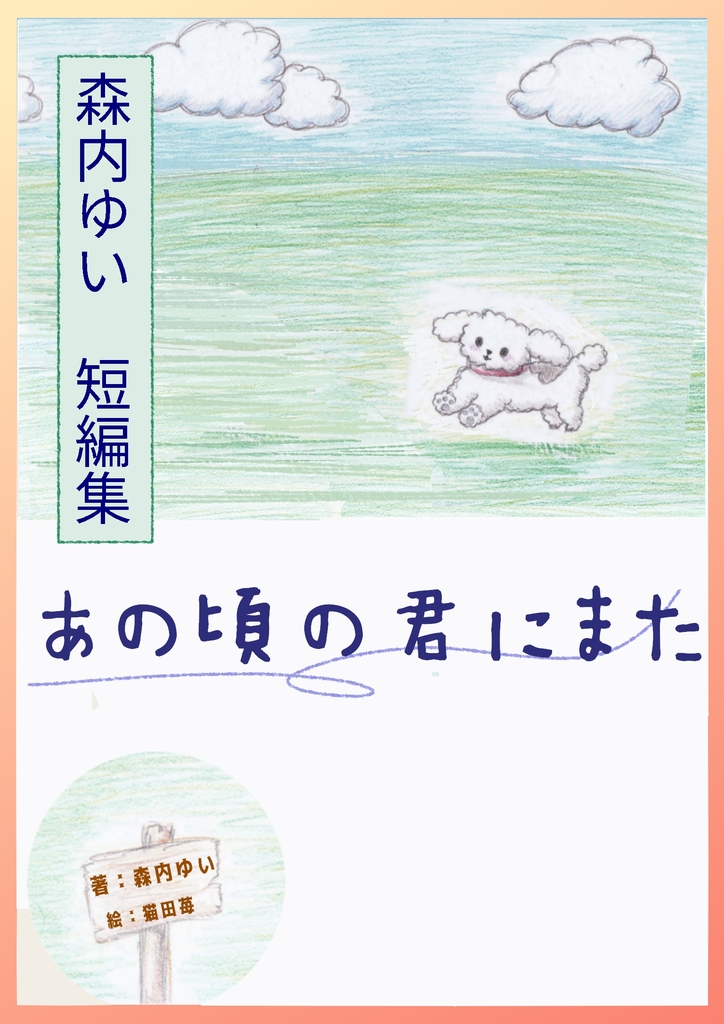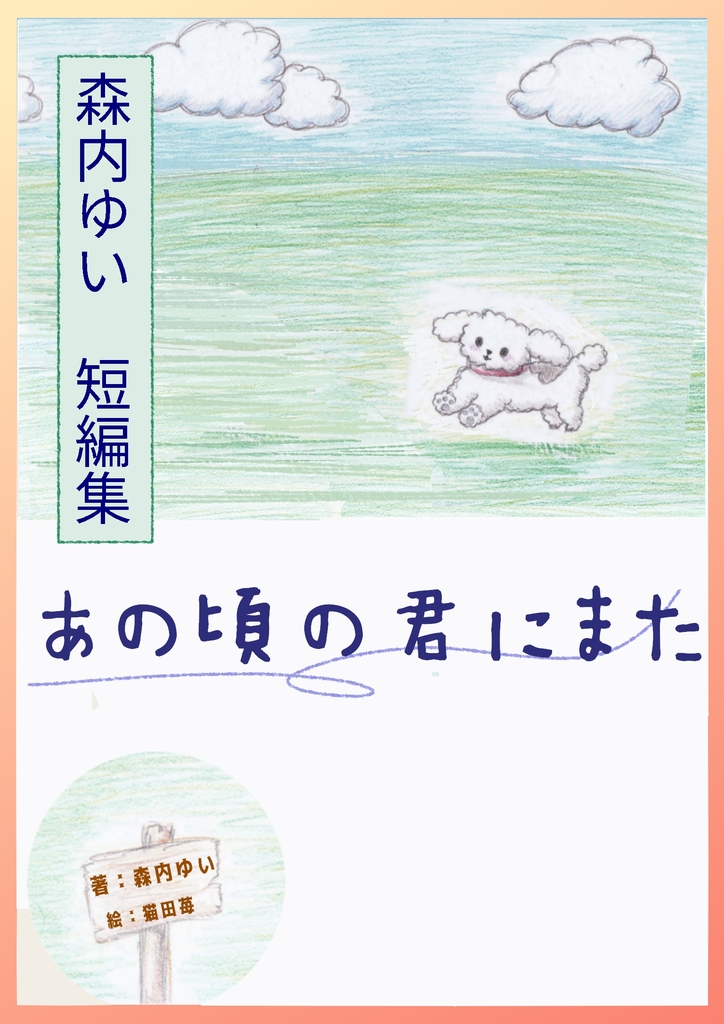
【書籍情報】
| タイトル | 森内ゆい 短編集 あの頃の君にまた |
| 著者 | 森内ゆい |
| イラスト | 猫田苺 |
| レーベル | 詠月文庫 |
| 価格 | 300円 |
| あらすじ | 人とペット、あるいは、人と人の出会いと別れ。そこには、笑顔もあれば涙もあっていい――。短いエピソード13作を一冊にまとめました。 |
【本文立ち読み】
森内ゆい 短編集 あの頃の君にまた
[著]森内ゆい[イラスト]猫田苺
目次
かえっておいで……
あの頃の君にまた
いつも一緒にいようね
誰でもいいから
次は幸せになりなよ
そこに君はもういないのに
花一輪のさよなら
ここで生きてていいのかな
ずっと五歳
気付かなかった
夢のままで消えないで
ずっと見守ってくれた人
その思いやりをありがとう
かえっておいで……
受験が終わった。
肩の荷が下りたような気がした。
でも、ウキウキした解放感や幸福感とは違う。
玄関のドアを開けた瞬間、胸に重くのしかかるものがある。
四年間愛していた中型犬が、尻尾を振り迎えてくれることがなくなった家。
玄関から続く廊下を走ってくることもなく、ドアを開けた自分の部屋で嬉しそうに出迎えてくれることもなく。
「なあ、受験終わったよ。たくさん散歩ができる。約束しただろ? やっと時間ができたのに、なんでいないんだよ。帰ってきて、じゃれついて顔や手をなめてくれよ」
声に出すと、静まり返った部屋が余計に広く感じられた。
もう会えない。
受験勉強からの解放より大きな喪失感。
涙が止まらなくなった。
あの日、親の誘いで、保健所に一緒に行ったのは気まぐれだった。
子どものとき犬を飼っていたから、飼いたいならかまわないという両親に連れられて行ったけれど、それは両親の希望でいろいろな犬をショップ以外で見てみたいという好奇心だ。
犬は好きだったけれど、中学2年生のぼくには、決定権はないと思っていた。
白い蛍光灯の下、狭いケージが並んでいた。
小さな鳴き声や床に当たる爪の音が響く。
犬の臭いが充満し、耳障りな音が響く中で、一匹だけ静かにこちらを見つめている犬がいた。
茶色と白がまだらに混じった中型犬。尻尾は揺れていないのに、きれいな瞳はぼくをじっと見つめる。中学二年で何かと不安定だったぼくの心に、その眼差しが強く刺さった。
手続きを終え、犬は新しい首輪をつけられ、ぎこちなくぼくの隣を歩き始めた。
家に着くなり、父と母が「名前はどうする?」と盛り上がる。
ぼくは迷った末、二人に命名権を奪われないうちに
「ベル」
と短く呼びやすい二文字の名前を口にした。
最初の夜。
犬は落ち着かず、部屋の隅から隅を歩き回った。
ぼくの布団のそばに敷いた毛布にようやく丸くなったとき、吐息が静かに部屋を満たす。同じ部屋に自分以外のいのち。不安もあったけれど、それ以上に胸の奥からわきあがる温かさ。
翌朝、まだ薄暗いうちに眠い目をこすりながら犬を連れて外に出ると、冷たい空気と一緒に新しい生活の匂いがした。
首輪に慣れない犬は、最初の散歩で何度も立ち止まった。
リードを引きすぎれば足をすくませるし、緩めれば急に走り出そうとする。
ぼくは汗をかきながら
「こっちだよ」
と声をかける。
そのたびに犬は首をかしげ、不思議そうにぼくを見上げる。
ぎこちない歩調は、まるでお互いのリズムを探しているようだった。
春には道端にたんぽぽが咲き、犬は花粉でくしゃみをした。
夏には夕立を避けて急いで帰り、二人してびしょ濡れになった。
秋には落ち葉を踏みしめ、犬はカサカサという音に夢中になった。
冬には吐く息が白く、犬の背中に雪が降り積もった。
季節が巡るたび、ぼくらは同じ道を歩きながら、新しい思い出を重ねていった。
食卓につく時間には、犬は必ず横にちょこんと座り、期待の眼差しを向ける。
母が用意したドッグフードを器に入れると、夢中で食べ始める音が響く。
たまにぼくがパンのかけらを落とすと、犬はしっぽを振って宝物のように受け取った。
そんな小さな瞬間に、言葉にできない満ち足りた幸福があった。
散歩の帰り道、犬は必ずぼくの足の横に寄り添うようになった。
リードがなくても離れないんじゃないかと錯覚するほど。
夜、勉強机に向かうぼくの足元で眠る姿を見て、気持ちが落ち着いた。
「君がいるだけで頑張れる! 希望の大学はまだハードル高いんだ。でも合格するぞー!」
冬が近づくにつれ、ぼくの机の上には参考書と赤いペンが積み重なっていった。
朝も夜も、ページをめくる音と鉛筆の走る音ばかり。
散歩の時間が短くなり、時には「今日は行けない、ごめんな?」と玄関先で謝る日もあった。
犬は何も言わず、ただ尻尾を小さく振りながらぼくの足元に座っていた。
机にかじりついていると、視線を感じることがあった。
振り返ると、犬がじっとこちらを見つめている。
遊んでほしいのか、それともただ見守っているのか。
その無言の瞳は、時に重たく、時に温かかった。
ぼくはため息をつきながら「あと少しで終わるから」と心の中で答えた。
休日、友達の声が外から聞こえても、ぼくは机に向かい続けた。
横で丸くなる犬に、つい声をかける。
「ごめんな、遊べなくて」
犬は耳をぴくりと動かすだけで、何事もなかったように目を閉じた。
その仕草が、かえって罪悪感として胸に刺さった。
夜更け。シャーペンの音が止まらない部屋で、犬は机の下に潜り込んで眠っていた。
足先に伝わる温もりが、心をいっぱいにしている不安を少しずつ和らげる。
「一人じゃない」
言葉にはしなくても、確かにそう感じられた。
受験の壁に向かうぼくの隣には、いつも変わらず小さな体が寄り添っていた。
カレンダーに赤く丸をつけた受験日まで、あと数週間。
「試験が終わったら、いっぱい散歩しような」
机に向かいながら、ぼくは何度もそう犬に語りかけた。
犬は意味を理解していないはずなのに、耳を立ててこちらを見つめ、尻尾を振る。
その姿は、約束をちゃんと聞いてくれたように見えた。
勉強の合間に連れ出す散歩は、いつのまにか時間が短くなっていた。
犬は文句を言わない。ただ、立ち止まるたびにぼくを見上げる。
「ごめん、今日は早く帰ろう」
そう口にすると、犬は素直に歩き出した。
その従順さが、逆に心を締めつけた。
玄関で靴ひもを結ぶ気配に反応し、犬は必ず駆け寄ってくる。
散歩のときだけは、子犬のように跳ねるのが可愛い。
忙しさに追われても、その瞬間だけはぼくの顔もほころんだ。
どんなに時間が短くても、犬の瞳には変わらぬ輝きが宿る。
ある日の散歩で、犬の足取りが少し重いことに気づいた。
坂道を登るとき、息が荒くなるのが早い。
「疲れたのか?」
声をかけると、犬は尻尾を振って答える。
無理に見える元気さを、ぼくはそのとき深く考えなかった。
「試験が終わったら、たくさん歩こう」
犬の体にどれほど残された時間があるのか、ぼくは知らなかった。
続きは製品でお楽しみください