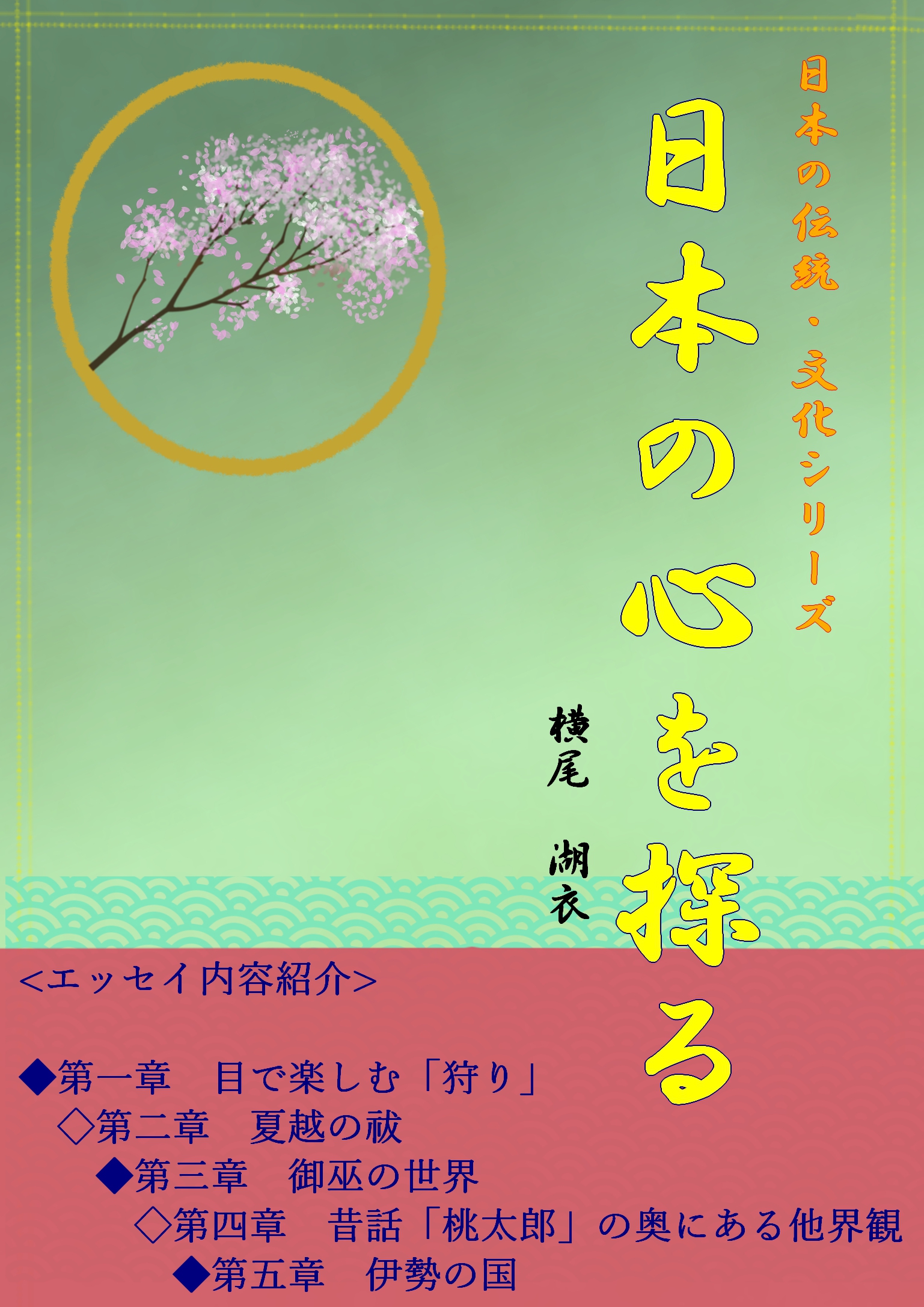【書籍情報】
| タイトル | 玉の輿なんて似合いませんっ ~女刑事はVIPに逆逮捕される~ |
| 著者 | 朝陽ゆりね |
| イラスト | 稲垣のん |
| レーベル | ヘリアンサス文庫 |
| 価格 | 800円 |
| あらすじ | 捜査一課の刑事である真織は、特命を受けてシンガポールの大富豪である榛原瞬の護衛に就くことに。「SPでもないのに、なんで私が」なんて思っていたが、空港で待っていたら四歳のリントまで一緒とは。「聞いてない!」真織の不満はMAX。しかし瞬もリントも紳士で、一緒にいたら楽しくて…。二十日間の同居はあっと言う間に終わりそう、そう思っていたら瞬に激しく求められ、「好きだ」との甘い言葉を囁かれる。シンガポールに来てほしい――そんな、どうしたらいいの!? |
【本文立ち読み】
「シュン~だっこ~」
「はいはい」
目の前で二十代半ばくらいの美麗な男が小さな子どもを抱き上げた。
(どうして子どもがいるの? ……聞いてないけど)
見るからに高そうな白いスーツを着ているそのイケメンと、三、四歳くらいの男の子。こちらも有名ブランドのロゴマークが入っている服を着ている。ここ羽田空港までプライベートジェットでやってきたのだから姿を見ずとも富豪だとわかっていたものの、実際に目の当たりにして、改めて痛感させられた。
(でも……いくらイケメンでも白のスーツはなくない?)
驚くべきはその容姿で、若い男のほうはどこのスターだと思うほどスマートで秀麗な顔をしている。身長はおそらく一八〇センチくらい。すらりと細く、手足が長い。モデルだと言われても疑わないだろう。子どものほうはパッと見では性別がわからないほど愛らしい顔立ちだった。
この男がマルタイ――つまり警護対象者の榛原《はいばら》瞬《しゅん》、三十歳。シンガポールに国籍を持つ日系シンガポール人で、祖父母がシンガポールに渡って財を成し、現在、金融界に名を馳せるヘーゼルグリッターグループ会長の孫だ。非常に優秀で、十代で米国ハーバード大学に入学し、MBAを取得。現在はCEOである父親の片腕として複数の子会社の社長を務めていると聞く。
彼が休暇で日本にやってくるのにあわせ、その身を守るよう、なんと警視総監御自らに命令を下されたのが昨夜のことだ。
(どうして警備部じゃなくて私なのよ。ボディガードならSPの連中にさせればいいじゃない。しかも男のマルタイに女の私がつくの!? さらにコブ付きだなんて……聞いてない)
愛らしい子どもの顔を眺めながら、速水《はやみ》真織《まおり》はぼんやりと思った。
真織は現在、警視庁刑事部捜査一課・第一特殊犯捜査・特殊犯捜査第二係に籍を置く刑事だ。特殊犯捜査は恐喝や脅迫を主とした部署で、重要人のボディガードをする部署ではない。
階級は警部補、役職は主任。この年にして、また女で、警視庁本庁、捜査一課の刑事なのだから優秀であることは自他ともに認めるところだ。
大卒の場合、警察学校での警官修行期間は半年であり、最初に昇格試験を受けられるのが二年後。受かれば巡査部長だから、もう一回受けてパスした、ということになる。一日机に向かっている仕事ではなく、毎日足を引きずって走り回っているので勉強などする時間も余裕もない。それでもなんとかコツコツ勉強を重ね、ここまできた。
警察学校を出たらまずは所轄のハコバン勤務、つまり交番のお巡りさんか、あるいは交通課に配属されて交通違反の取り締まりなどを行う。これらの業務を経て希望職を口にできる状態になるので、二十八歳で本庁勤務、刑事の憧れである捜査一課に籍を置いていることは本当に素晴らしい――と評価されていることは名誉だが、当然周囲から受ける嫉妬は大きい。実際に嫌な思いをすること多々であった。
そんな真織は、昨夜、仕事を終えて「今日こそ早く帰ろう」と思った矢先、内線で呼び出されたのだ。それが警視総監なのだから背筋が凍る思いがした。
(私、なんかやらかしたっけ……)
顔は蒼ざめ、冷や汗脂汗がにじんで流れている。ドキドキしながら総監室に向かい、受けた命令が、シンガポールの富豪がバカンスで訪日するので、滞在中これについて安全を確保するように――だった。
その時はあまりに急な話で、さらに命令を下す相手が相手だったので、「なぜ、私?」と思う余裕など暇もなかった。
「あなたがボディガード?」
榛原瞬に話しかけられ、真織ははっと我に返った。
(いけない、職務中だった!)
小さく息を吸い、警察官独特の敬礼をもって挨拶をする。
「警視庁、刑事部捜査一課・第一特殊犯捜査・特殊犯捜査第二係の速水です。榛原さんの身辺警護を拝命しております。本日から二十日間、よろしくお願いいたします」
「こちらこそ、よろしく。ヘーゼルグリッターグループの榛原瞬です。こちらは甥のリント」
瞬はうっすら微笑みながら手を出した。真織もそれに応じて握手をする。
「僕らは確かにVIPかもしれないけど、堅苦しいのは嫌だから僕のことはシュン瞬でいいし、リントのこともリントでいいので。なぁ、リント」
「…………」
「リント? どうした?」
「おこってる」
「怒ってる? 誰が?」
榛原リントはピッと真織を指さした。瞬の視線が指先を追い、真織で止まる。
「怒ってるって。どうして?」
「……いえ、怒ってなど」
「おこってる!」
すかさずリントのツッコミが入った。同時に真織の喉がくっとわずかに鳴るが、さすがに二人には聞こえはしなかった。
「怒ってるそうだけど。子どもって敏感なんだよね。もっとにこやかに頼むよ」
「あ、はい。あ、いえ、怒ってなどおりません」
「顔に〝なんでここに子どもがいるんだ?〟とか〝どうして刑事の自分がボディガードをしなくちゃいけないんだ?〟と書いてあるけど」
「! すみません」
反射的に謝ってしまった。すると瞬がプッとふき出し、リントの頭をくりくりと撫でまわした。
「リントもそんなにかわいげのない顔しないで。このおばちゃんが日本にいる間、僕らの身を守ってくれるんだ。お仕事大変なのに、僕らのために時間を割いてくれるんだからね」
おばちゃんだぁ!?
思わず怒鳴りそうになって、真織は咄嗟に目を逸らし、口をつぐんだ。さらにその唇に力を入れる。おかげで閉じられた部分が波打っているような気がする。
「まもる?」
「そ。危険なことがないように、身をていして僕らを守ってくれるんだよ」
なんてことを! とこれまた言いそうになったが、瞬時に意図を察した。こんな子どもが「身をていして」なんて言葉の意味を知っているわけがない。つまり真織をからかい、その反応を見て楽しんでいるのだ。
(そういえば……)
――榛原瞬くんは優秀すぎて、少々我々を困らせてくれるが悪意はない。本当にいい男だ。そのことを理解して接してほしい。
と、言われたことを思い出した。
その時は、「総監だってキャリアなんだから優秀でしょう」とそっちに意識が取られたものの、総監はちゃんと大事なことを伝えてくれていたのだ。
(……反省)
うなだれる真織の前で二人のやりとりは続いている。
「じゃー、つおいの?」
「うん。〝つおい〟よ、とーっても」
「ホント!? わー! ならいいー」
強いって言われても……と思わず言いそうになってまたまた唇に力を込める。女であることを配慮してほしいなんてこれっぽっちも思っていない。自分は警視庁の刑事だ。凶悪犯が目の前にいたら突っ込んでいくだけの決意と覚悟はとっくにしている。
リントの機嫌がよくなったところで瞬が真織に顔を向けた。
「速水さん、ファーストネームは?」
「え? あ、名前……ですか。真織ですが」
「マオリね。了解。で、マオリは何歳なの?」
タラリと冷や汗が流れる気分が。
(それ、思いっきり、セクハラなんですけど)
なんて思うが、にこにこと悪意の微塵もないきれいな笑顔で問われると注意する意欲が失せる。真織は、はあ、と小さくため息を落とし、素直に答えた。
「……二十八です」
「へぇ、若いじゃない。そうなんだ。凛々しい顔立ちだから、もっといってるのかと思ったよ。リント、おばちゃんじゃなく、おねえちゃんだったよ」
「おねーちゃんだぁー。シュン、まちがっちゃダメだよ」
「そうだね。失礼だったね」
にこにこにこにこにこ……
対して真織は、こめかみと頬と口角のあたりがヒクヒクと痙攣するのがわかった。
(褒められているのか、バカにされているのか、わからないっ! けど、総監にも念押しされているから、怒っていると思われることはNG! 頑張れ、私!)
そんな真織に瞬がますます微笑みを深める。
「とにかく、よろしく」
「……いえ、こちらこそ」
「リント、マオリおねえちゃんが抱っこしてくれるって」
「わーい! つおいマオー、だっこぉ!」
えぇぇ!? と思いながらも、リントが両手を差し出して伸ばしたので、真織も反射的に腕を伸ばしてしまった。
(あ)
と、思った時には、すでにリントは真織の腕の中だった。
「マオー、やわらかーいっ」
真織の胸に顔をぎゅっと押しつけると、二、三度、額をつけた状態でグリグリと左右に振った
(ちょっ!)
このシチュエーションをどう処理すべきなのか。子どもが胸に顔を埋めてグリグリやっている。やわらかいとはやはりバストのことだろうか、いや、こんな子どもがセクハラを口にするはずがない。ここは怒ってはいけない。母性本能フル回転で温かく接しなければ!
そう思ったところで、真織はいきなりリントが静かになったことに気がついた。
(え?)
寝ている。
「あ、あの、リントくん?」
「ちょっと疲れたみたいだね。飛行機の中ではしゃぎまわっていたから」
「……そう、なんですか」
「悪いね。重いだろう。預かるよ」
「あ、いえ、まったく大丈夫です。それよりも、榛原さんもリントくんも日本語を話すんですね」
「…………」
瞬はそれまで浮かべていた笑みを消し、真剣なまなざしで真織の胸に顔を押しつけて眠っているリントを見つめている。
「あの……榛原さん?」
もう一度名前を呼ぶと、瞬ははっとしたように目を瞬いた。
「瞬でいいって」
「…………」
真織の目が、「任務であなたについているんです、そんな呼び方ができるわけないでしょ!」と語っているが、礼儀正しく無言で通す。すると瞬はまた微笑みを浮かべた。
「ほら、瞬って呼んでよ。僕は日系だし、外見や話す言葉は日本人と遜色ないけど、れっきとしたシンガポール人だ。だから習慣は違うんだよ。さぁ、マオリ、瞬って呼ぶんだ」
「……ですが」
マオリのさらなる抵抗に、瞬は上を向いて少し考えたような仕草をすると、すぐに顔を真織に戻してうっすら微笑んだ。
「わかったよ。マオリは仕事、任務で僕の警護をしている。だから礼儀を通さないといけないと考えているんだ。馴れ馴れしいのはいけない、ってわけだろ? うん。ならば僕もそのつもりで対応する。速水さん、僕はファミリーネームで呼ばれることはあまりよしとしない。瞬と呼ぶように命じる」
はぁ? と顎が落ちそうになり、真織は慌ててその顎に力を込めた。
「あの……」
「でなければ上原《うえはら》さんにクレームを入れるよ。でも、解任はしないから、そのつもりで」
「……わかりました」
上原とは警視総監の名だ。真織は瞬時に悟った。
(どうして私が選ばれたのかはわからないけど、この人が警視総監と個人的なつながりにあることはわかった)
なんらか事情があって警察がVIPの身を護ることになったのだ、と思っていたものの、どうやら単純に警視総監の〝お友達〟であるので、こそっと呼ばれてこそっと命じられたようだ。
――内密の対応だから情報の取り扱いは慎重に頼む。
難しい顔をして言われたので、てっきり〝一本釣り〟にあったのだと思っていたのだが、まさかよもやプライベートの要件で呼び出されたとは。いや、確証はないが。ちなみに〝一本釣り〟とは、上が直属の上司を通さず、ジカに内々にて任務を命ずることを指す。
(もぉー!)
どれほど悔しくても、真織に抵抗の余地はナノ・レベルで残ってはいないようだ。
「……瞬、さん」
「〝さん〟はいらない」
「……瞬」
「よくできました。で、質問に戻るけど」
真織の目が「質問?」と問うているものの、瞬はかまわず続けた。
「我が家は母と義理の姉がシンガポール人だけど、母は日本語学校に通っていたこともあってきわめて堪能なんだ。だから家族内では日本語でやりとりしている。でも外ではリントも含め英語だ。中国語は、会話はわかるが堪能じゃない」
そこまで聞いて、「あ、そうだった、この子も日本語をしゃべるってことに驚いて聞いたんだった」と思い出した。そのことに気づいているのかいないのかわからないが、瞬はわずかに頷いた。
「とはいえリントはまだ四歳で、日本語と英語はごちゃまぜだから、そのあたりは寛容に頼むよ」
「それはもちろんです。こんな小さな子どもですから」
「マオリに抱っこされていろいろ思い出したのかもしれないな」
いろいろ、とは?
尋ねそうになったが、瞬の表情が暗いのでなんだか言い出せなかった。
眠っているリントが真織のジャケットの襟を小さな手でぎゅっと強く握りしめている姿を見つめている様子はなんだか尋常ではない感じがするからだ。
「まぁ、その話はマンションについてからするよ。行こう」
そう言って瞬が歩き始めた。
「どちらのホテルに宿泊されるんですか?」
「いや、ホテルじゃない。マンションだよ」
「……マンション?」
「そう。従業員の気配がどうにも嫌でね。知り合いを通じて空いている部屋を賃貸したんだ。ここが住所」
渡された紙を見ると六本木に建つ高級タワーワンションのそれだとすぐにわかった。
「自炊になるけど、よろしく」
(それは私に家事をしろということ?)
そう思うものの、それ以前の疑問がある。空いている部屋を借りたとはどういうことだ?と。高級マンションを二十日間だけ借りられたのか? いや、そもそも賃貸物件なのか? 真織の頭の中はクエスチョンマークでいっぱいだ。
「買い手が決まるまで好きなだけ借りていいとのことだった。まぁ、色をつけての交渉なんだけど、二つ返事で了解してくれたからよかったよ。だから心配しなくていいよ」
別に心配なんかしていないけど……と、思わず言いそうになって慌てて口をつぐんだ。
(いけない。この人の軽口と優しげな印象からつい言葉が出てきそうになる。気をつけないと。しっかりするのよ、真織!)
真織は改めて心に活を入れた。
「で、六本木まで電車で行くの?」
「いえ、車でお迎えにまいりましたが……あ、子どもさんが同行とは聞いていなかったので、チャイルドシートを用意していませんでした」
「なるほど、そうだね。買っていこう」
「child seat??」
ついさっき寝落ちって気持ちよさそうに寝入っていたリントが、いきなり顔を上げて口を挟んだので真織は飛び上がりそうになった。一瞬、狸寝入りだった!? と思ったものの、眠そうにかわいい手で目をこすっているので純粋に目が覚めたのだろう。
(私ってヤだな……日々の仕事とすさんだ生活にすっかり汚れてしまっている気がするわ……)
と、ぼんやり思った。
「そうそう、child seatだよ。リント専用のかっこいいseatだ」
「リントせんよー? わーい!」
腕の中で無邪気に笑うリントを見下ろしながら、さらにぼんやり思う。
(さすが外国人。こんなちびっこでも発音は完璧……あ、待て、さっき瞬さん〝クレーム〟って言った。ってことは私が聞き取りやすいよう、わざとカタカナ英語を使ったってこと? 失敬な。私だって英会話は勉強してるんだから)
心の中でブチブチ文句を言いながら、真織はリントを抱っこしたまま瞬の後に追随した。
続きは製品でお楽しみください