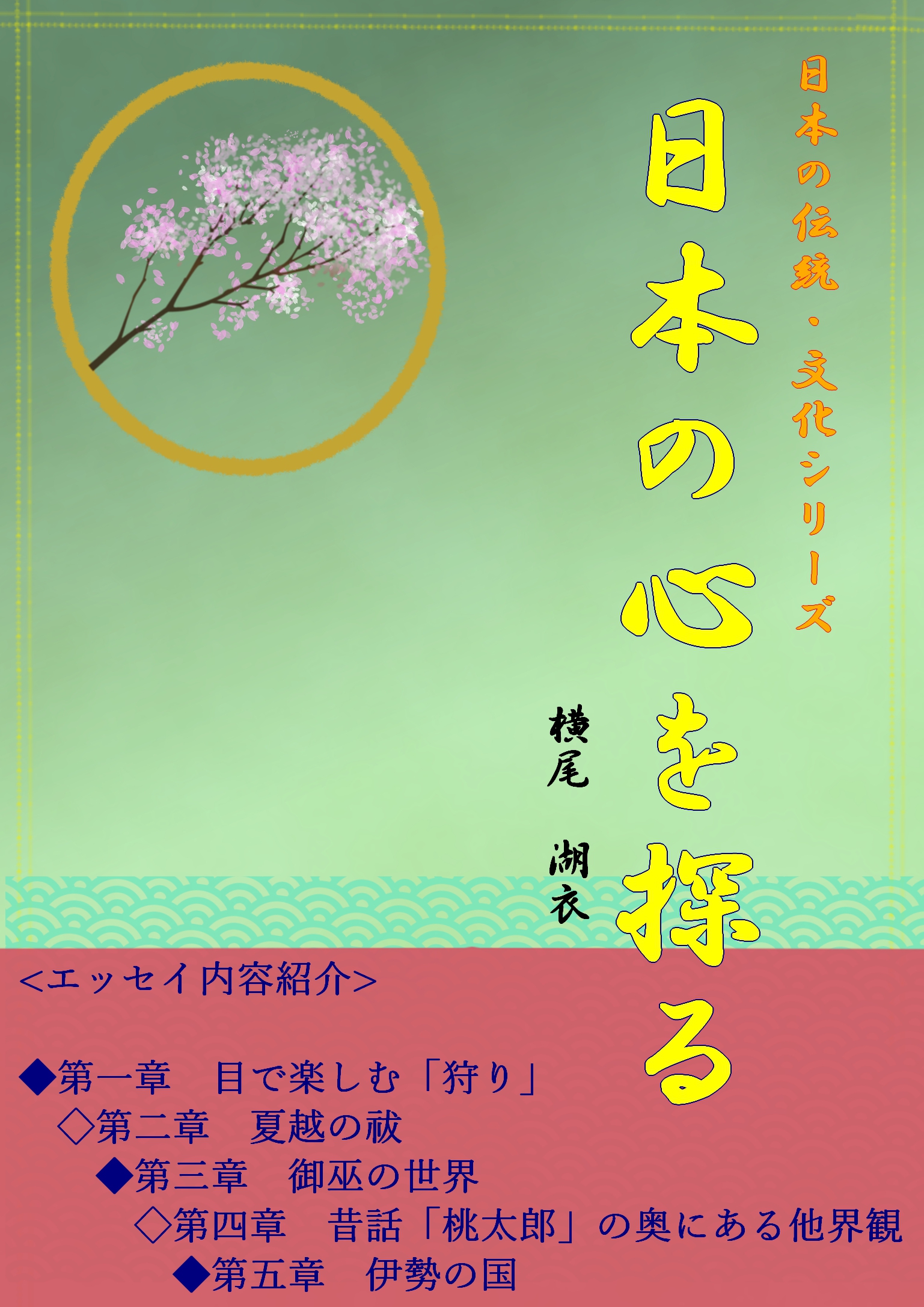【書籍情報】
| タイトル | 夏色 |
| 著者 | 猫宮乾 |
| イラスト | あす |
| レーベル | フリチラリア文庫 |
| 価格 | 500円+税 |
| あらすじ | 回復魔力を活かして働いているバイルの元に、ある日査察として魔術医療塔経営者のライスがやって来る。何かと抱きついてくるのを振り払うのが面倒になって放置する内に、それは自然な風景となる。日常は大切、だけど価値観が違う二人がそれぞれの世界を守るために戦うお話。 |
【本文立ち読み】
夏色
[著]猫宮乾
[イラスト]あす
※この作品は縦書きでレイアウトされています。
※この作品はフィクションです。実在の人物、団体、事件とは一切関係ありません。
目次
夏色
【番外】湖畔の家での休日
【番外】子供達のキス
【番外】名前
【一】魔術医療総合塔
二階の研究室の窓を開けて、バイル=エステルハートは庭の木の枝を見た。黄緑色の小鳥が止まっている。初夏の風に、彼の黒い髪が揺れた。煙草を一本銜え、銀のオイルライターで火を点けたバイルは、白衣のポケットにシガレットケースをしまう。
史上最年少で、魔術医療師となったのは十三年前の事である。現在、二十八歳――ここまで回復魔術一本で生きてきた。人は彼を、回復魔術の天才と呼ぶし、本人にもその自負がある。骨ばった長い指で挟んだ煙草を吸い込み、煙を吐く。一見不健康だが、この煙草は、バイルが魔術生成した人工物で、ニコチンの代わりにカロリーが摂取できる。
忙しすぎて、食事をしている暇がない。これは、この魔術医療総合塔グリモワールで働く魔術医療師の、ほぼ共通の悩みだ。少しつった猫のような黒い瞳を瞬かせ、バイルは煙を吐き出した。午後の診療時間は既に始まっている。だが午前の分が終わったのも、午後の診療時間に入ってからだ。三分くらいは休憩して良いだろうと彼は考えていた。だが、回復魔術科はマシな方である。
魔術医療総合塔グリモワールには、三つの診療科と二つの附属機関がある。
一つ目は、一般診療科。魔術薬学を用いて、怪我や疾患を治す。病院といえば普通はここだ。魔術医療師といえば、多くはここの所属である。
二つ目は、回復魔術科。バイルが所属している、魔術による直接回復を促す科だ。人体を治癒・再生すると言っても良い。
三つ目が、魔導具医療科。魔導具を用いて義肢を作ったり、心臓に魔導ペースメーカーを入れたりする。バイルの友人のグレンが、現在一番優秀な魔導具専門の魔術医療師だ。
附属機関は、魔術医療学校と――経営財団である。なお、この魔術医療塔を作り、お給料を支払っているのも、受付や入退院手続きをするのも、経営財団機関の担当となる。王家の分家であるレストハーミエル侯爵家が経営財団機関のトップだだ。魔術医療塔の総合玄関の壁写真にも、大きく経営者院長として『ライス=レストハーミエル侯爵』と書いてある。しかし十三年間も働いているが、一回もバイルは、そのライス氏を見た事が無かった。写真の顔は知っているが。
煙草を吸い終え――つまり食事が終わったので、バイルは仕事に戻った。
歩く度に白衣が揺れる。魔力がこもっているIDカードを首元から下げて、塔の廊下を進んだ。回復魔術科の患者やスタッフ達が気づいて、バイルに視線を投げかける。バイルは人気者だ。若干口が正直すぎる部分はあるが、気持ちの良い性格をしているからだろう。腕の良い魔術医療師というのは、それだけで七難を隠してもらえるものだ。
「お疲れ様」
午後の診察が終わったのは、夜の八時を回った頃だった。自動販売機脇の飲食スペース――即ち煙草でカロリーを吸収する場所に立ったバイルに、友人のグレンが歩み寄った。顔を上げたバイルがニッと笑う。唇の右端だけを持ち上げて笑うのは、バイルの癖だ。
それにしても、疲れた。午後の診療は、本来は四時で終わりだ。手術が入っていたとしても、余程の緊急手術でなければ、それは定時の間に済むスケジュールとなっている。そして本日は緊急手術は無かったし、昨日も無かった。だが、昨日も今日も八時まで診察をしていた。単純に患者の数が多すぎるのである。
「甘いものでも食べたい気分だよ」
魔導自動販売機の前に立ち、煙草を銜えたままでグレンが言った。指先が甘ったるいココアのボタンを押している。バイルにはこれが信じられない。バイルは、甘い物が苦手なのだ。
「よくそんなものが飲めるな」
「疲れてるとね、俺は欲しくなるんだよ」
「気がしれない。俺は甘い物なんて、大本命に『あーん』とかされない限り、絶対に生涯口にしない」
「君は寂しい独り身で、結婚の当てもゼロだから、つまり一生食べる事は無いという自虐で良いの?」
グレンが目を細めて視線を向ける。ココアを手にしながら、『どうなの?』と視線で聞くと、バイルが顔を背けて誤魔化した。二人の吐き出す煙が、近くの観葉植物型排煙機に吸収されている。実際にはこの煙にも無菌効果があったりするのだが、魔術医療塔では、至る所にこの観葉植物型排煙機が並んでいる。見た目が煙草であるから、誤解した人々から設置の要望があったらしい。
「お前こそなんだよ、それは惚気か? 婚約者様がいらっしゃるパルツピザン大公爵家の跡取り様はさすがに違うな」
バイルの友人であるこの魔導具専門家は、秋に結婚が決まっている。バイルも招待状を貰った。グレン=パルツピザンは、この国の第二王子殿下と生まれつき許嫁関係だったのだと、バイルは聞いていた。王家と許嫁というのが、やはり高位貴族という感じである。が、魔術医療塔においては、爵位や身分は関係無いという暗黙の了解がある。だから普段はバイルも爵位を持ち出さないし、口にも出さない。
女性が生まれなくなって、早八十年。魔術戦争の後遺症だ。だから現在、この国の女性は、高齢者ばかりである。そこで生まれた技術が、魔術医療による男性妊娠だ。これにより、一時期数百万人まで落ち込んだ人口も、少しずつ戻ってきたと言われている。だが戦後世代の二人には、生まれた時から結婚や恋愛というものは、同性同士で行うものだったし、子供もまた男が産むものだという感覚だから、いまいち実感は無い。
モクモクと二人は煙を吐き出しながら、顔を見合わせた。グレンは今年、三十二歳だ。バイルの五つ年上である。バイルが史上最年少の十五歳で学校を卒業した時、規定通りの年数をぴったり終えて、二十歳でグレンは学校を卒業した。二人は同期である。科目は異なるが。バイルの中で、友人と言われればグレンだし、グレンにとってもそうだ。
その時――前方でざわめきが起きた。二人は揃って動きを止める。何事だろうかと考えたバイルとグレンは、ほぼ同時に視線を向けた。コツコツと靴音が響いてくる。それに合わせるように、カツカツと杖を突く音もする。二人は、もう一度顔を見合わせてから、今度はじっくりとそちらを見た。
見れば、夏だというのに黒い外套を羽織った青年が歩いてくる。左手に持っている杖は金色だ。飴色の靴は踵が高い。チョコレート色の髪の上には、黒いシルクハットを被っている。だが、それらは、奇抜な顔面の効果で、すぐにどうでも良くなった。顔を白塗りにした青年は、頬の右側に赤いダイヤ、左側に黒いスペードの小さなマークをペイントしている。道化師のようだ。ビスクドールのような付け睫毛が、顔に影を落としていて、目の周囲だけが、青と黒の中間色で染められている。異様な風体だ。だが、バイルとグレンが目を見開いたのは、その外見に驚いたからではない。
ずらっと付き人を連れて歩いてきた青年は、楽しそうな顔をしている。バイルは、外套の下に見える紋章入りの赤い貴族服を確認してから、再度青年の顔を見た。すると、目が合った。驚いてバイルが小さく息を呑んだ時、青年が立ち止まった。丁度、バイルとグレンの正面だ。
「……ライス=レストハーミエル侯爵?」
思わずバイルは呟いた。
――本物か? と、玄関の写真そのままの姿をした、青年の出現に虚を突かれていた。
「お見知りおき頂き、光栄です。バイル=エステルハート先生」
すると穏やかに、この魔術医療塔の最高権力者が微笑した。バイルは天才と誉れ高いし、自分でもそう思っていたから、知られていても不思議はないと考える。
「グレン=パルツピザン先生も、こんばんは」
「こんばんは」
グレンも驚いた顔をした。二人は、さらっと煙草を魔術で消失させて、頭を下げた。すると会釈を返して、ライス=レストハーミエル侯爵が歩みを再開した。付き人達も歩き始める。ポカンとしたまま、バイルとグレンはそれを見送った。
一行が去ってから、バイルが新しい煙草を銜えた。
「本当に存在したんだな」
「そりゃあ魔術医療塔が機能していて、俺達にお給料が出る以上は、存在するんじゃない?」
「俺、初めて見たけど。グレンは?」
「俺もだよ。まさか名前を知られてるとは思ってなかった。名前が知られていたとしても、顔と一致しているとは、全然考えてなかったよ」
そんなやり取りをしてから、二人はそれぞれ帰宅した。グレンは、明日から一週間の出張らしい。暫しのお別れだなとバイルは思った。
【二】査察
――翌日。
「はぁ? 査察?」
回復魔術科の朝の打ち合わせの際、バイルが声を上げた。眉を顰め、非常に面倒くさそうな顔で、知らせを持ってきた他の魔術医療師達を見る。
「え、ええ……経営財団機関から、直接の申し出でして……」
「どこの誰が来るんだよ? 相手をしている時間があるのか? 無いぞ? 勝手に入って勝手に歩いて勝手に調べて勝手に帰れと伝えておけ」
バイルが言うと、報告している同僚が引きつった笑みを浮かべた。
「そ、それが……ライス様が直々にいらっしゃるそうでして……ぜ、ぜひ、天才と誉れ高い、エステルハート先生の手腕を間近で見たいとの事で……」
「俺? 確かに俺は天才だ。だから死ぬほど忙しいと――……」
言いかけて、バイルは声を飲み込んだ。昨日見た、奇抜な青年の顔が頭に浮かんだからだ。査察日程は、昨日には既に決まっていたはずだ。わざわざ昨夜、自分の前を通りかかったのは、果たして偶然だったのだろうか? そう考えながら、バイルは、室内を見回した。
「――今日、レイスは?」
「レイス先生でしたら、ライス様をお迎えに……」
「ふぅん」
バイルは腕を組んだ。レイス=レストハーミエルという同僚医師の顔を思い出す。春に学校を卒業したばかりの新米魔術医療師だが、既にこの回復魔術科では、バイルと腕を競う優秀な人物である。若干二十一歳。丁度入れ替わるように退職した彼の父は、王家の御典医に栄転した。
そのままレストハーミエル派の魔術医療師を掌握した若き期待の星は――……バイルと非常に仲が悪い。
古くからの回復魔術理論信奉者で経営財団の主要人物であるレストハーミエル侯爵家派と、バイルのような現場で力ある最先端の魔術医療師派は、昔から対立している。考えてみると、その、レイスの兄が、ライスだ――と、バイルは思い当たった。
「――これまで魔術医療塔の中に顔を出した事の無い経営者様が、弟の就職と同時にいらっしゃるなんてなぁ」
バイルが吐き捨てるように言ってから、煙草を銜えた。周囲の人々が、やっと気づいたのかという風に、大きく頷いている。医療面ではバイルは天才だが、それ以外の部分までそうであるとは言えない。傍から見ている限り、どう考えても、レストハーミエル派の後ろ盾である最高責任者が、バイルに釘を刺しに来るとしか思えない。
扉が開いたのは、その時の事である。
「バイル先生!」
入ってきたのは、噂されていたレイスである。
「今日から兄上が来る。来るなと伝えたが、もう玄関だ。大至急、診察に向かった方が良い。兄上は、頭がおかしい事で評判なんだ。迷惑をかけると思うが、まぁ迷惑だろうな。そこは我慢してくれ」
レイスの口から、バイルを心配するような言葉が飛び出した。これには、バイルを含め、回復魔術科の多くの魔術医療師達が首を傾げた。
「――お前の兄なんだろ? レイスをいじめるなーって、俺に言いに来るんじゃないのか?」
バイルが率直に尋ねた。するとレストが咽せた。
「馬鹿にしているのか?」
「基本、な」
「否定をしろ――あのな、いくら俺の権力欲欲求が強かろうとも、仕事に差し障るようなやり方などしない」
断言したレイスに、バイルは頷いた。当然だ。患者の命が、かかっている。
「だったら追い返してくれ」
「もう来たんだ」
「お前が相手をすれば済むだろう」
「違うんだ。兄上はバイル先生が相手をしてくれなければ、給料を八十パーセント、カットすると言ってきた」
その言葉に、室内に激震が走った。客観的に考えればあり得ないように思えるが――レストハーミエル家が過去に、給料カットを実際に行い、医療魔術師側が侯爵家の要求を呑む形で折れた事例は、実は腐るほどあるのだ。確かに命を救う職業は大切であるが、経営者の方が権力が強い場合もある。
更にこの国では、塔を一歩出れば、貴族には逆らってはならない事になっている。レストハーミエル侯爵家よりも高位であるのは、グレンのパルツピザン大公爵家と王家くらいのものである。さらにレストハーミエル侯爵家は王家の分家なので、この国では非常に高位の存在だ。
結果的に、室内には「バイル先生頑張って下さい」という声が溢れた。
【続きは製品でお楽しみください】