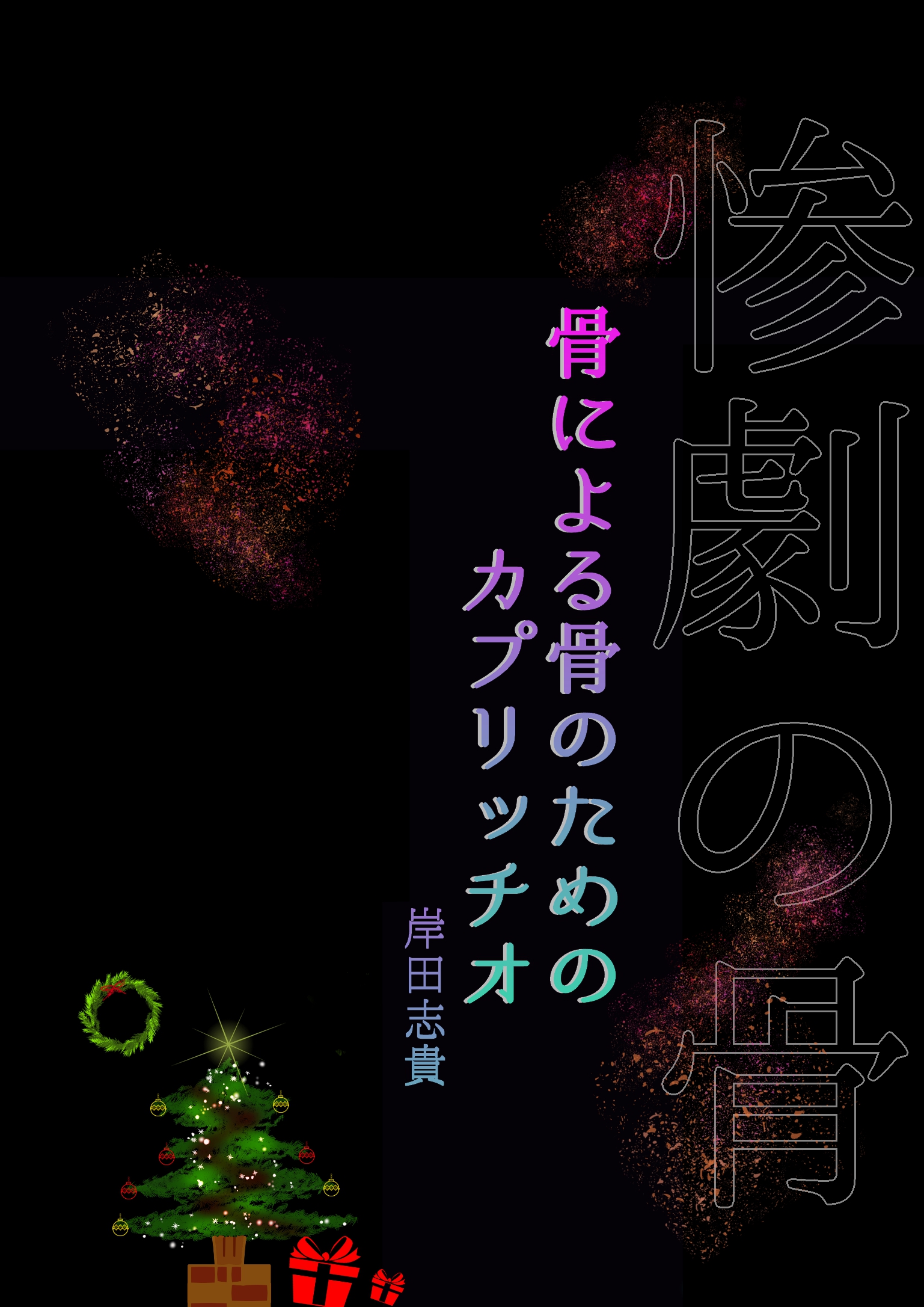【書籍情報】
| タイトル | キッス・ミー -悪を憎んで正義を撃つ― |
| 著者 | 水城優 |
| イラスト | |
| レーベル | ペリドット文庫 |
| 価格 | 450円+税 |
| あらすじ | 二十二世紀末、人類の環境汚染によって、絶滅に瀕している亜種等(人間以外の種の総称)たち。彼らは、生き残りをかけて神々に新たな救世主を求める。神の命によって召喚された天を衝く怪物トールマン(長身族)が人類粛清に動き出す。時を同じくして、狂気の科学者ドクターΣによって生み出された世界最強兵器、人造人間ΣI号も秘密研究所で覚醒する。 最大の見どころは、人類に替わる種として、対峙する両者の攻防戦が最大の見どころです。 物語自体はかなりシリアスですが、人造人間ΣI号を取り巻く人間関係を、ときにはユーモアを、ときには切なるない思いをちりばめながら作品に深みを与えて行きたいです |
【本文立ち読み】
キッス・ミー -悪を憎んで正義を撃つ―
[著]水城 優
遠い、遠い過去の話。
大陸ミロスに伝説の銃があった。
名をMRジャスティスという。
この銃は、正義を心から愛し、諸悪の根源を絶つといわれている。
彼?のモットーは、〝悪を憎んで正義を撃つ〟である。
兵器工学の権威であるワイアット教授によって武器と生物を掛け合わせて生み出されたものの一体である。
この武器生物を総称して武装獣と呼ぶ。
教授の作り出した武装獣には、皆、人間や動物のように心を宿している。
彼らは純粋無垢な生物として誕生。その後、その武器を最初に手にした者の影響を色濃く受け継ぎ共に成長していく。
その者が善人であれば正義の心を、悪人であれば邪な心を宿してしまう。
大陸ミロスの西部は、その大半が不毛の荒野であった。
人が暮らせる場所は数少ない。
そこに生きる者たちは、一獲千金の夢に破れた者や盗賊まがいの連中が数多い。
そのため、力のない者や弱い者から先に死んでいく。まさに弱肉強食の世界である。
だから西部では、力こそ正義なのである。
当然、ここには法や秩序などは存在しない。
この無法者が支配する地域に一人の保安官が現れた。
彼の名は、ジャッジ・ミロスという。
彼は、MRジャスティスの所有者にて善人中の善人であった。
そんな正義の心を持つジャッジだったが、ある日、突然消息を絶つ。
それから十年が過ぎていった。
西部は、再びギャングや盗賊どもが跋扈する無法地帯となった。
そして人々は救世主を求めた。
その者がこの西部にひとすじの光を指してくれることを信じて……。
プロローグ
とぼとぼと、砂漠を一人の旅人が横断している。
したが、その姿はいささか奇異なものに映る。
なぜなら、文明の利器の乏しいこの時代、砂漠を旅することはまさに命懸けなのだ。
その旅人の姿とは……。
それは、筋骨たくましいマッチョな男でもなければ、タフガイのカーボーイでもない。
テンガロンハットから栗毛色の髪を靡かせ、ポンチョを着こなし、ミニスカートから艶めかしい太腿がこれ見よがしにむき出しになっている。
そう、この旅人は女性なのだ。
それもまだ十代であろうか、うら若き乙女に見える。
砂漠を一人の少女が横断している。
それだけでも奇異に映るのだが、それよりも何よりも彼女が命を預けている獣がどえらく人の目を惹く。
砂漠を横断するともなれば、少なからず動物の力を借りねばならない。
代表的な動物とは、馬、駱駝、驢馬など砂漠に似つかわしい動物をだれしも思い浮かべる。
だがこの少女がチョイスしている動物とは……。
何と牛なのである。しかもホルスタイン。
少女とホルスタインがとぼとぼと砂漠を横断しているのだ。
どう見ても人の目には奇異なものに映ってしまう。
少女の名前は、キッス・ミー。
これは、れっきとした彼女の本名である。
そしてホルスタインの名前はモウモウという。
彼は言葉がしゃべれる不思議な牛で、生まれてこの方、自分を馬だと信じて生きているから始末に悪い。
グゥ~、グゥ~。
砂漠の荒野に何とも言えない不協和音が響き渡る。
「お腹すいたわねえ、モウモウ」
キッスがお腹を摩りながら、相棒に語りかける。
「確か三日前に食べた昼飯が最後だ、ウンモウ~」
モウモウの背には、毛布代わりになる外套のハザ、空の羊の革袋、火付け道具などの日用品の類を入れる袋を担いでいたが、食べ物はどこを探しても一かけらも出てこない。
それもそのはず、キッスとモウモウが街を出たのは一週間前の話である。
次の街まで四日と見越して必要な水や食糧を調達したのだが、目測を誤り、砂漠で迷子になってすでに一週間が経とうとしている。
もちろん食糧どころか水も尽き果て、砂漠を当てもなく彷徨っているのである。
砂漠を進めど進めど食べ物の『た』の字にも出っくわさない。
出会うのは白骨化した動物の屍と枯れた灌木ぐらいである。
今の二人の最大の関心事は食べ物のことばかり……。
キッスもモウモウも身も心も疲れ果てていた。
グゥ~、グゥ~。
元気がいいのは、腹の虫だけである。
すると、どこからとなく、二人に声をかけてくる者がいた。
「おい、私を助けろ!」
その声から連想されるのは、几帳面そうで、どこか冷たい感じのする男の声であった。
キッスとモウモウは、慌てて辺りを見回すものの、どこにも人影らしきものは見当たらない。
見渡す限りここは砂漠のど真ん中、蜿蜒と砂の道だけ続いている。
「気のせいね。さっ、行くわよ」
キッスはそういうとその場を通り過ぎようとした。
だが、何者かが必死に叫ぶ。
「このバカ者、人がこうして頼んでいるのに無視していってしまうのか、情け知らずが……」
今度は、割とはっきりと相手の声が聞こえる。
これは、空腹や暑さからくる幻聴ではない。
冷たく感情のかけらもない声だが、必死に助けを求めていることだけははっきりと伝わってくる。
キッスは、モウモウから下りると、あたりを注意深く探し始めた。
だが、探せど探せど、人らしき者の姿はどこにも見当たらない。
「だれよ。助けを求めておいて隠れているなんて、いやらしい人ねえ」
キッスは相手がなかなか姿を現さないことに腹を立てていた。
砂地を歩き回り、立てなくてもいい腹を立てたことで、更なる悲鳴を腹の虫が上げていた。
「ちょいといい加減してちょうだい。どこに隠れているのかいいなさいよ」
キッスは地面から突き出た平たい岩にどかんと腰を下ろすと、見えない相手に悪態をついた。
「痛い、痛い。何をする。苦しい」
声の主が再び声を発した。
今度はどうやらすぐ近くから聞こえる。
腰掛けながら周囲を慎重に探るが、やっぱり人っ子一人見当たらない。
「もう、いったいあなたはだれ? どこにいるのよ、まったくもう」
キッスの忍耐も限界にきていた。
「私はここだ。君の尻の下にいる」
相変わらず冷たく感情の無い声だったが、必死さだけはなぜか伝わってくる。
慌てて可愛いヒップをどけてみると、その平たい石の上に蠢くものが見て取れる。
それは砂を被っていた。
丁寧に砂を拭うと、不思議な形をしている金属片がそこにあった。
全長が二十五~三十センチほどの大きさで、先端が細長く丸い筒状の形をしている。後部の方は握りと指がかかりそうな……。
「これって拳銃みたいな形をしているわね」
「そうだ。私は拳銃だ」
冷静さを取り戻したかのように拳銃が会話の続きを始める。
拳銃がしゃべり出したので、キッスは慌てて手を引っ込める。
「嘘ばっかり、だれかが隠れて話しているんでしょう」
キッスは鼻からこの手の話を信用しない。
とはいっても、ここは砂漠のど真ん中である。
人が隠れそうなところはどこにもないのだ。
「猜疑心もここまで度を越していると、人間という種の愚かさを痛感させられるよ」
拳銃は、キッスを小ばかにしたように言い放つ。
さしものキッスもこの摩訶不思議な現象を信じずにはいられなかった。
「拳銃がしゃべるなんて信じられない。けど、これは事実だわ」
「そうかな。さっきから見ていたが、君の旅の友は牛のくせに言葉をしゃべるじゃないか。そっちの方がよっぽど信じられないよ」
拳銃がつかさず突っ込みを入れる。
「おらは牛ではないぞ。馬だぞ。ウンモウ~」
それまで黙っていたモウモウが、牛と呼ばれて猛抗議した。
「それはいいとして、いったいあんたはなんなの?」
キッスが言葉をしゃべるおかしな拳銃に猛然と詰め寄った。
「人にものを尋ねるのであれば、そちらから最初に名乗るのが礼儀ではいではないだろうか」
拳銃のいかにも上から目線の態度に少し腹を立てたが、それも一理あると思い、キッスは自己紹介を始めた。
「あたしはキッス・ミー。それでこっちが旅の友モウモウ。それであなたは?」
「なんで初対面の君といきなり口づけを交わさなくてならないのだ。気持ち悪い。うげぇ~。」
しゃべる拳銃が〝口づけ〟と聞いて露骨に不快な感情を露わにする。
「失礼しちゃうわね。ちょっとあんた、誤解しないでね。キッス・ミーっていうのはね、あっちの意味じゃなくて、あ・た・し・の・本・名なのよ。わかった。それとあっちの意味でいったとしたって、こんなかわいい女の子とチューできるのよ。それなのに、うげぇーとはなによ。うげぇーとは……。失礼しちゃうわね、ふん」
キッスは、プイと顔を横に背け機嫌を損ねる。
実のところキッスは、自己紹介があまり好きではなかった。
苗字はともかく、名前を付けるのならもう少しましな名前を付けてほしかったと思う。
名付け親の養父は、だれからも祝福が受けられる子に育つようにと願いを込めてつけてくれたのだが、合体するととんでもない意味になる。
彼女の十数年の人生で自分の名前をフルネームでいうと、ほとんど百パーセントの確率で皆、口づけをしてくるからたまらない。
イケメン風の男の子だったら、まだしも寄ってくるのは同性か子どもたちが多い。
だが、それはまだましなほうである。
前の街では酒場で食事をした際、ついうっかり名前を聞かれて、キッス・ミーと答えてしまった途端、荒くれ者たちからチュー、チューといわれて絡まれた。
この名前は、今のところキッスにとっては疫病神以外の何物でもなかった。
「私の名前は、MRジャスティス。この世で唯一、意志を持った拳銃だ」
MRジャスティスが誇らしげに名乗る。
「何で拳銃のくせに意志もあって、言葉をしゃべれるのよ」
キッスが言葉をしゃべる摩訶不思議な拳銃に喰ってかかる。
「拳銃のくせにとはなんだ。拳銃が意志をもち、言葉をしゃべってどこが悪い。文句があるのなら、私を作ったワイアット教授にいってくれ」
冷静な口調ではあったが、キッスにバカにされたことに少なからず自尊心を傷つけられ、怒りを露わにしている。
どうやらただの偏屈者ではないらしい。
「ワイアット教授って、だれ?」
「私の生みの親で兵器工学の権威でもある。彼は武器と生物を掛け合わせて、人を傷つけない武器を作り出そうとしていた」
キッスがつかさず突っ込みを入る。
「それって矛盾した考えじゃないの。武器は多かれ少なかれ、人や生き物を傷つけるもの。いや殺してしまうものと考えてもおかしくないわ。それなのに人を傷つけない武器を作り出そうだなんておかしいじゃないの」
「ここで君と兵器談義をしていても始まらない。ここで大事なことはここから君が私を救い出してくれるかどうかということだ」
MRジャスティスが切実に語る。
「わかったわ。遠回りしたけど、助けてほしいとはどういうことなの?」
キッスは、MRジャスティスから詳しく事情を訊くことにした。
「私は以前正義の保安官に使えていたが、彼が突如私を残して消息を絶ってしまった。その後の記憶は私にも残っていない。気づいて目が覚めたら、砂と石ころしかない砂漠に放置されていた。そして長い年月こうして耐え忍んでいたのだ」
MRジャスティスは悲惨な過去を物語る。
「ふ~ん。そうなの」
キッスが興味なさそうな感想を漏らす。
「私の十年間の悲痛の叫びをたった八文字で片づけてしまうなんて……」
MRジャスティスが初めて感情らしきものを露わにした。
「へ~え。あなたも感情を高ぶらせることがあるんだ」
キッスは、茶目っ気たっぷりにウィンクして見せた。
【続きは製品でお楽しみください】